【抵当権抹消Q&A】住宅ローン完済後の手続き、司法書士がスッキリ解説!

住宅ローンを完済されると、大きな安心感と共に達成感を覚えられることでしょう。しかし、実はもう一つ大切な手続きが残っていることをご存知でしょうか?それが「抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)」の手続きです。
「抵当権抹消って何?」「自分でできるの?」「費用はどれくらいかかるの?」など、多くの方が疑問に思われることでしょう。この記事では、そんな抵当権抹消に関するあらゆる疑問について、私たち司法書士法人槐事務所がQ&A形式で分かりやすくお答えします。
手続きがご不安な方、お忙しい方は、私たち専門家がお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。
それでは、早速見ていきましょう!
目次
第1章:抵当権抹消のキホン – まずはこれだけ知っておこう!
Q1. 「抵当権抹消」って、そもそも何ですか?なぜ必要なのですか?
A1. 抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際に、ご自宅の土地や建物に金融機関が設定する権利のことです。
万が一ローンの返済が滞った場合に、金融機関がその不動産を競売にかけるなどして貸したお金を回収できるようにするためのものです。
住宅ローンを全額返済すると、この抵当権は実質的には意味をなさなくなります。しかし、自動的に消えるわけではなく、法務局に「抵当権を消してください」という申請(抵当権抹消登記)をしなければ、登記簿上には残ったままになります。 この抵当権を登記簿から消す手続きが「抵当権抹消登記」です。
Q2. もし抵当権抹消をしなかったら、どんなデメリットがありますか?
A. 住宅ローンを完済していても、登記簿に抵当権が残ったままだと、主に以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
- 不動産を売却しにくい: 買主から見ると、まだローンが残っているように見え、敬遠される可能性があります。通常、売却時には抵当権の抹消が条件となります。
- 新たな融資を受けにくい: その不動産を担保に新たにお金を借りようとする場合、抵当権が残っていると審査に影響が出ることがあります。
- 相続の際に手続きが複雑になることも: 相続が発生した際、相続人が抵当権抹消の手続きを行うことになりますが、時間が経つほど書類の再発行の手間が増え、手続きが煩雑になったりする可能性があります。
- 金融機関の再編等で手続きが面倒になることも: 金融機関が合併したり名称変更したりすると、必要な書類が増えるなど、手続きが複雑になる場合があります。
完済したら、なるべく早く手続きを済ませることをお勧めします。
Q3. 抵当権抹消の手続きに、期限はありますか? いつまでにやればいいですか?
A. 法律上の明確な期限はありません。しかし、Q2. でお答えしたようなデメリットを避けるため、また、住宅ローンを完済したら速やかに手続きを行うのが一般的です。時間が経つほど手続きが煩雑になるリスクも高まります。
Q4. 手続きには、全部でどれくらいの時間がかかりますか?
A. ご自身で手続きをされる場合、書類の準備から法務局への申請、完了まで、スムーズに進めば2週間~1ヶ月程度が目安です。ただし、書類に不備があったり、法務局が混み合っていたりすると、さらに時間がかかることもあります。
司法書士にご依頼いただいた場合は、必要書類をお預かりしてから通常1~2週間程度で完了しますが、法務局の処理状況によって変動します。
第2章:自分でチャレンジ! – 抵当権抹消を自分で行う場合
Q5. 抵当権抹消の手続きは、自分でできますか? 難しいですか?
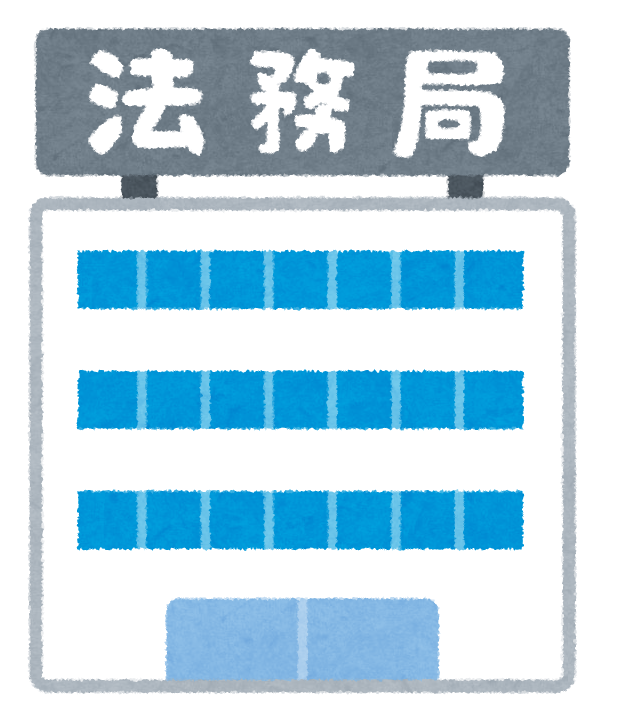
A. はい、ご自身で行うことも可能です。手続き自体は、必要な書類を揃えて法務局に申請するというものです。ただし、登記申請書の作成や、添付書類の確認など、ある程度の知識と手間は必要になります。普段あまり馴染みのない作業ですので、難しく感じる方もいらっしゃるかもしれません。法務局の窓口で相談しながら進めることもできますが、相談時間は限られており、基本的には平日の日中のみとなります。
Q6. 自分で手続きする場合、どんなメリットとデメリットがありますか?
A. 一般的には、次のようなメリットとデメリットが考えられます。
- メリット:
- 司法書士に支払う報酬がかからないため、費用を抑えられます。
- デメリット:
- 書類の準備や申請書の作成に手間と時間がかかります。
- 法務局へ何度も足を運ぶ必要がある場合もあります(特に書類に不備があった場合)。
- 書類の不備で申請が却下されると、やり直しになり、さらに時間がかかります。
- 手続きに関する知識をある程度調べる必要があります。
Q7. 自分で手続きする場合、費用はどれくらいかかりますか?

A. ご自身で手続きする場合にかかる主な費用は以下の通りです。
- 登録免許税: 不動産1個につき1,000円です。例えば、土地1筆と建物1棟の場合は、2,000円となります。マンションの場合は、土地の敷地権の数によって変わることがあります(例えば、敷地1筆+建物1棟で2,000円となります)。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用: 事前に登記内容を確認したり、完了後に確認したりする場合に必要です。1通600円(オンライン請求・郵送受取なら520円、オンライン請求・窓口受取なら490円)です。
- その他: 郵送費(郵送で申請する場合)、交通費などがかかる場合があります。
司法書士への報酬はかかりませんが、これらの実費は必要になります。
Q8. 自分で手続きする場合、どんな書類が必要で、どこで手に入りますか?
A. 一般的には、主に以下の書類が必要になります。多くは住宅ローン完済後に金融機関から渡されます。
- 登記済証(権利証)または登記識別情報通知: 抵当権を設定した際に金融機関が法務局から受領するものです。
- 解除証書(または放棄証書、弁済証書など): 金融機関が抵当権を解除したことを証明する書類です。
- 委任状: 金融機関からの委任状が必要になります。
- (ご自身で作成)抵当権抹消登記申請書: 法務局のホームページから様式をダウンロードできます。
書類に不足や不備がないか、有効期限は切れていないかなどをしっかり確認しましょう。
Q9. 登記申請書はどこでもらえますか? 書き方の見本はありますか?
A. 登記申請書の様式や記載例は、法務局のホームページで入手できます。管轄の法務局の窓口でも相談に乗ってもらえたり、記載例が備え付けられていたりすることがあります。
Q10. 法務局ってどこにあるの? 平日しかやっていませんか?
A. 管轄の法務局は、法務局のホームページで調べることができます。そして、申請は、不動産の所在地ごとに管轄する法務局が決まっています。例えば、多摩市にある不動産であれば、東京法務局府中支局といった具合です。
法務局は土日祝日、年末年始は閉庁しています。不動産登記の窓口対応時間は、職員の働き方改革を推進するため、令和6年1月4日から、基本的に午前9時から午後5時までとなりました。
第3章:専門家におまかせ! – 司法書士に依頼する場合
Q11. 司法書士に抵当権抹消をお願いするメリットは何ですか?

A. 司法書士に依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 手間と時間を大幅に削減できる: 面倒な書類の準備や申請書の作成、法務局への訪問などをすべて任せられます。
- 正確かつ確実に手続きが完了する: 専門家が書類のチェックから申請まで行うため、不備による遅延ややり直しのリスクがほとんどありません。
- 平日に時間を取る必要がない: お仕事などで忙しい方でも、スムーズに手続きを進められます。
- 複雑なケースにも対応可能: 相続が絡む場合や、書類を紛失した場合など、ご自身では対応が難しいケースでも相談に乗ってもらえます。
- 精神的な安心感: 専門家に任せることで、「本当にこれで大丈夫だろうか?」という不安から解放されます。
Q12. 司法書士に頼むと、費用はどれくらいかかりますか?
A. 司法書士に依頼する場合の費用は、主に「登録免許税などの実費」と「司法書士報酬」で構成されます。司法書士報酬は、事務所や案件の難易度によって異なりますが、事務所によって異なります。
正確な費用については、ご依頼前にお見積もりをご確認ください。私たち司法書士法人槐事務所でも、無料でお見積もりを承っております。
Q13. どんな場合に司法書士にお願いした方がいいですか?
A. 以下のような方には、司法書士への依頼をおすすめします。
- 平日に法務局へ行く時間がない方
- 書類の作成や手続きに不安がある方、面倒だと感じる方
- 手続きをミスなく、確実に早く済ませたい方
- 金融機関から渡された書類の有効期限が迫っている方
- 相続が発生している、住所や氏名に変更があるなど、手続きが少し複雑になりそうな方
- 遠方の不動産の抵当権抹消をしたい方
Q14. 司法書士法人槐事務所に依頼する場合の流れを教えてください。

A. はい、当事務所にご依頼いただく場合の基本的な流れは以下の通りです。
- お問い合わせ・ご相談: まずはお電話やメール、当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
- お見積もり・ご説明: 状況をお伺いし、お手続きの流れや費用についてご説明します。
- ご依頼・書類のお預かり: ご納得いただけましたら、正式にご依頼いただき、金融機関から交付された書類等をお預かりします。委任状にご署名・ご捺印いただきます。
- 当事務所にて手続き代行: 登記申請書の作成から法務局への申請まで、責任をもって行います。
- 手続き完了・書類のご返却: 登記が完了しましたら、登記完了証やご返却書類をお渡しいたします。
ご来所いただかなくても、郵送等でのやり取りで手続きを進めることも可能です。お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 平日 9:00-18:00
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください第4章:費用について – 何にどれくらいかかるの?
Q15. 抵当権抹消の費用には、どんなものが含まれますか?

A. 抵当権抹消にかかる費用は、大きく分けて以下の2つです。
- 実費:
- 登録免許税: Q7でご説明した通り、不動産1個につき1,000円です。
- 登記事項証明書取得費用: 事前確認や完了後確認のために取得する場合にかかります。
- 郵送費、交通費など。
- 司法書士報酬(司法書士に依頼する場合のみ):
- 登記申請書の作成、法務局への申請代行、関連書類のチェックなどに対する専門家としての手数料です。
Q16. 登録免許税の「不動産1個につき1,000円」というのは、具体的にどう数えるのですか?
A. 例えば、一戸建ての場合、通常は「土地」と「建物」の2つの不動産として扱われますので、登録免許税は2,000円になります。
マンションの場合、「敷地権の対象となる土地(1筆とは限りません)」1筆につき不動産1個として計算します。
第5章:必要書類について – これがないと始まらない!
Q17. 金融機関からもらう書類の中で、特に重要なものは何ですか?
A. 金融機関から受け取る書類はどれも重要ですが、特に以下のものは紛失しないように注意が必要です。
- 登記済証(権利証)または登記識別情報通知: これを紛失すると、再発行はされず、別途特別な手続きが必要になり、費用や時間も余計にかかってしまいます。
- 解除証書(または放棄証書、弁済証書など): これも再発行に手間がかかる場合があります。
- 委任状:登記申請をしないまま放置しているうちに金融機関の代表取締役が交代してしまうと、手間が増えますので、早めの手続きをお勧めします。
書類を受け取ったら、すぐに中身を確認し、大切に保管してください。
Q18. 金融機関からもらった書類をなくしてしまったら、どうすればいいですか?
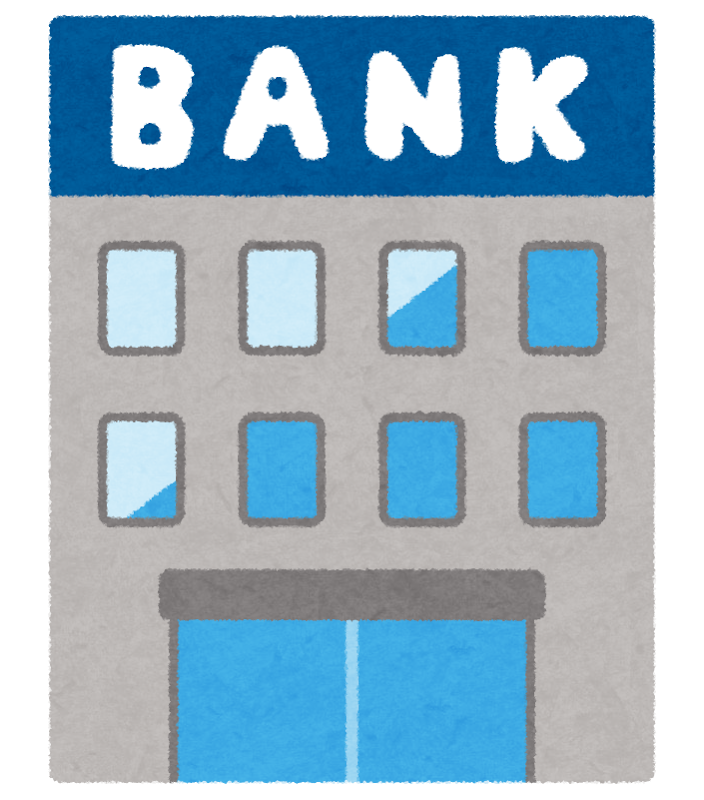
A. まずは落ち着いて、もう一度よく探してみてください。それでも見つからない場合は、金融機関に連絡し、再発行が可能かどうか相談してみましょう。書類によっては再発行に費用や時間がかかる場合があります。
特に「登記済証(権利証)」や「登記識別情報通知」を紛失した場合は、法務局からの事前通知制度を利用するなどの代替手続きが必要となり、通常よりも手続きが複雑になります。このような場合は、速やかに司法書士にご相談いただくことをお勧めします。
第6章:困ったとき・特殊なケース – こんな場合はどうする?
Q19. 家の持ち主(登記名義人)が亡くなっている場合、抵当権抹消はどうなりますか?
A. 家の持ち主が亡くなった後に住宅ローンが返済(抵当権が解除)されたのか、住宅ローンが返済(抵当権が解除)された後に家の持ち主が亡くなったか、時期の先後で、手続が異なります。
- 家の持ち主が亡くなった後に住宅ローンが返済(抵当権が解除)された
- まず相続登記(不動産の名義を相続人に変更する登記)を行う必要があります。
- 相続登記が完了した後、新しい名義人となった相続人が抵当権抹消の手続きを行います。
- 相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請することも可能です。
- 住宅ローンが返済(抵当権が解除)され後に家の持ち主が亡くなった
- 相続登記(不動産の名義を相続人に変更する登記)を行わずに抵当権抹消の手続きができます。しかし、登記申請書の書き方は難しくなります。
不動産の所有者が亡くなられている場合、相続が絡む場合は手続きが複雑になりますので、司法書士にご相談いただくことをお勧めします。
Q20. 登記簿の住所や名前が、今の住所や名前と違う場合は、どうすればいいですか?
A. 抵当権抹消登記の前提として、登記簿上の住所や氏名が現在のものと異なっている場合(引越しによる住所変更、結婚・離婚による氏名変更など)は、「登記名義人表示変更登記」を先に行うか、抵当権抹消登記と同時に行う必要があります。この変更登記にも、住民票や戸籍謄本(抄本)などの書類が必要となり、別途登録免許税(不動産1個につき1,000円)がかかります。
Q21. 昔の抵当権で、金融機関が合併したり、もう存在しなかったりする場合はどうすればいいですか?
A. 金融機関が合併や会社分割、商号変更などをしている場合、その変遷を証明する書類(閉鎖事項証明書など)が必要になることがあります。
また、すでに解散してしまった金融機関の抵当権を抹消するには、法的手続きが必要になるなど、非常に複雑なケースもあります。 このような場合は、ご自身で対応するのは困難なことが多いので、早めに司法書士にご相談ください。
Q22. 抵当権が複数設定されている場合はどうなりますか?
A. 複数の金融機関から借り入れをしていたり、追加融資を受けていたりすると、不動産に複数の抵当権が設定されていることがあります。それぞれの住宅ローンを完済するたびに、それぞれの抵当権について抹消手続きが必要です。 手続き自体は1つずつ行うことになりますが、まとめて司法書士に依頼することも可能です。
第7章:その他 – ちょっと気になること
Q23. 抵当権抹消が終わったら、何か証明書のようなものはもらえますか?
A. はい、法務局での抵当権抹消登記が完了すると、「登記完了証」が発行されます。これは、申請された登記が完了したことを証明する書類です。また、ご希望であれば、抵当権が抹消されたことを確認できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得することもできます(別途取得費用がかかります)。
司法書士にご依頼いただいた場合は、通常、これらの書類をお渡しします。
Q24. オンラインで抵当権抹消の申請はできますか?
A. はい、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、オンラインで申請することも可能です。ただし、電子署名や専用ソフトの準備などが必要となり、ある程度のITスキルが求められます。一般の方が利用するにはまだハードルが高い面もあります。
Q25. 抵当権抹消について、どこに相談すればいいですか?
A. ご自身で手続きを進める中で不明な点があれば、管轄の法務局の登記相談窓口で相談することができます。ただし、書類の作成代行は行っていません。 手続き全般のご相談や、代行をご希望の場合は、私たちのような司法書士にご相談ください。司法書士は登記の専門家ですので、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供できます。
まとめ:大切な不動産のために、忘れずに抵当権抹消を

ここまで、抵当権抹消に関する様々な疑問にお答えしてきました。少しでも皆様の不安や疑問の解消にお役立ていただけたでしょうか。
住宅ローンを完済されたら、抵当権抹消手続きは忘れずに行いましょう。ご自身で手続きする時間がない方、書類の準備や申請に不安を感じる方、手続きが複雑になりそうな方は、どうぞお気軽に私たち司法書士法人槐事務所にご相談ください。
経験豊富な司法書士が、お客様の大切な財産に関するお手続きを、親身になってサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 平日 9:00-18:00
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください




